11月29日(土)に、東北芸術工科大学で行われた第9回探究型学習研究大会で、本校の探究的な学習の取組み事例について、紺野陽人教諭が発表しました。その後、その取組みを経験した本校2年生の「セイタカアワダチソウの根に含まれる水溶性物質について」と「蔵王の樹氷はいつまで見られるのか」のテーマでそれぞれ研究をしている2つの班が、時折ユーモアも交えながら元気よく研究発表を行ってきました。これらの発表は、東北芸術工科大学の会場だけでなく、オンラインによる全国への配信も同時に行われました。本校の指導の流れやSSHの活動、そして生徒の発表を広く普及するのに大きく役に立った発表会となり、その後、他校からの問い合わせも多くいただきました。今後も、このような機会を利用して、本校の課題研究に関する知見を広め、課題研究に関する他校との協力関係が構築できれば良いと考えています。このような機会をご提供くださいました東北芸術工科大学の皆様に感謝申し上げます。
SSH関連カテゴリー: 探究学習・探究活動
12月2日(火)と3日(水)に東根市の特別天然記念物指定区域にて行われた、カクレトミヨ推定個体数調査に、本校2年生の課題研究でカクレトミヨの保全に取り組む3名が、東根市と清流の里おおとみ保全推進協議会、山形大学(半澤直人名誉教授)らと共に、トラップの設置からトラップの回収・捕獲個体数の確認までの調査に参加しました。初日は穏やかな日差しの下でのトラップの設置作業でした。しかし、3日は時折冷たい雨が降る中の作業でしたが、両日ともに胴長を履いて冷たい川に入り、二日間頑張って調査を行いました。2日目の様子はYTSのニュースで放送され(https://www.yts.co.jp/news/news-221733/)、また、山形新聞でも紹介されました。今回の調査により、昨年度よりも推定個体数は大きく減少していました。夏の高温と渇水の影響が出ているとのことでした。このようなところにも、地球温暖化の影響が出ていることを現場で感じてきました。
また、カクレトミヨは東根市が市の魚に指定している絶滅危惧IA類の生物ですが、市民や高校生の認知度は残念ながらまだ低いと思われます。よって、今後は、この魚の知名度を高める方に力点をおいて活動していく予定です。さらに、この研究が後輩に引き継がれ、カクレトミヨの保存に貢献していくことを期待しています。
左:カクレトミヨ 右:ドジョウ
10月10日(金)は、中学1年生から3年生の全校生徒を対象に、未来創造プロジェクトジュニアフィールドワークとして、探究学習をより深める時間として午後4時間を設定しました。自分たちの探究テーマに関連する内容について校外に出て関係機関を直接訪問し、情報を収集したり、試作や検証するための実験などを行ったりするなど、存分に探究活動に取り組みました。
※ 育成したい東桜コンピテンシーは次の5つです。
【実行力】【論理的思考力】【批判的思考力】【表現力・発信力】【創造力】
◆テーマと実験の様子を紹介します。
1年【スカート×自転車問題】 1年【靴の通気性が悪い問題】
自転車をこいだ時にめくれないようにする 運動の後の靴の中は熱気がこもってしまう。
磁石を利用して道具を作り、試してみた。 靴のシートの下を冷却したらどうなるか。
サーモグラフィで測ってみた。
1年【破けにくく動きやすいズボンを作りたい】 1年【雨の日でも軽くて滑らない杖を作ろう】
まずは布の耐性を調べてみた。コンクリート お年寄りの杖の先は雨の日は滑ってしまい
土、砂利の道路で転んだ場面を設定し、布 がち。持っている杖に、ひと工夫して
(毛、綿、ポリエステル等)の強さを調べた。 滑らない杖にしたい。
2年【廃棄されるさくらんぼの魅力を 2年【規格外の野菜をリメイクせよ】
作ろう】さくらんぼ染をした糸でコース 野菜の絵具を試作する。この日の目標は
ターやキーホルダーを編む。 完成形により近づけること。
2年【脳トレで脳に”NO!”と言わせない】
養護老人施設に訪問し、利用者さんとの交流やインタビューを行った。
介護士さん等職員の方にもお話をうががって、よりよいアイデイアを生もうとした。
3年【音楽は野菜の生育に影響を与えるのだろうか】 3年【太陽光パネルを様々な条件に
違う環境下で育てたラデッシュの細胞や繊維を 設置したときの違い】
顕微鏡で観察した。 実際に太陽の光を当てて発電させてみた。
他にも、3年生は次のようなテーマで検証実験をしています。
【自家製酵母の原料の違いによるパンの保存期間への影響】
【甘酒作りの方法を用いてデンプンから甘みを取り出せるか】
【バナナの皮から潤滑油成分を抽出するには】
【最速で倒れるドミノの配置・設計はどのようなものか】
【米ぬかを用いて水質を改善することはできるのか】
8月22日(金)に、未来創造プロジェクトにおける意見交流会を行いました。これまでの探究活動の内容を発表し合い、意見を交流することで、見方を広めていくとともに考えを深め、今後の探究活動の方向性を探っていくことをねらいにしています。
ここでは、東桜コンピテンシーの【表現力・発信力】【傾聴力】【批判的思考力】の育成もねらいます。
発表は、ポスターセッション形式で、1グループ20分を持ち時間とし、探究テーマの設定理由や今考えている探究の方法などを説明しました。
東北芸術工科大学より5名、山形大学より1名の先生方、そして山形大学理学部の学生さん5名(本校の卒業生)も助言者として来校いただきました。全学年、活発な発表が行われ、聞き手も疑問点を発表者に積極的に質問し、共によりよい探究となるようにと発言する前向きな姿勢がみられました。この意見交流会を通して、これまでの探究活動に新たな気づきが加わりました。今後はフィールドワークに臨み、さらなる探究の深まりをめざしていきます。


◆基本目標(6年間)と中学校の学年毎の大テーマとめあては添付資料の通りです。
◆ここまでの学習の様子を、学年毎に簡単に振り返ります。
【1学年】***つくる・うみだす【身近なところからデザイン(よりよく)する】*****
5月 探究の根幹となる「デザイン思考」「Yes, and」の考え方を理解
東北芸術工科大学の柚木泰彦教授をお招きし、「デザイン思考」について学びました。デザイン思考は、本校の探究学習「未来創造プロジェクト」を進める上で基盤となるイノベーション・メソッドです。ガイダンスでは、「Yes,and」の会話からアイデアを広げていく手法や「Will、Can、Need」の意識で課題を見出していくことを学びました。今年度も、3回にわたり「デザイン思考」について演習をしながら学びました。
- 1回目:ガイダンス 「デザイン思考」「Yes,and」「Will,Can,Need」
- 2回目:「身近な課題を通してアイディアの広げ方やまとめ方を学ぶ」
- 3回目:「他者の視点に立つ探究の基本姿勢を育む」友人のペンケースをデザインする
演習では、仲間との交流から課題を明確化するワークなどを行い、課題解決の糸口を探ることができました。「友人のペンケースをデザインする」では、友人の思いに寄り添って、自分たちでアイデアを膨らませたプロトタイプの制作を行いました。使用する人の思いに立ち、インタビューを繰り返してアイデアを考え、試作品を製作しました。
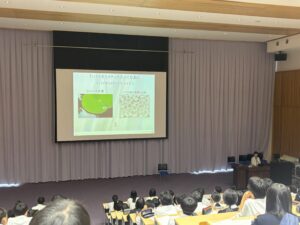


6月 「身近なモノ・コト に、なんでやねん!」で「探究のタネ」を見つける
身近なことから興味のタネを見つけ出すために、『身近ななんでやねん』をテーマに、1日の行動のリスト化し、「なんでやねん」とつっこみを書き、それらを細分化していきました。また、春課題『探究のタネ探し』(本校作成)を活用して、自分の困りごとだけではなく、家族の困りごとにも視野を広げました。
※本校使用テキスト 未来を拓く探究シリーズ「探究ナビ」Benesse 参照
7月 「探究のタネ」を育て、課題設定する
多面的に見通すためにワークシート(フイッシュボーン等)を用いて、探究のタネを育て、課題設定しました。その課題を解決するために、インタビューしてリサーチしたことなどをもとに、夏休みの活動も含めた探究計画を立てました。
※本校使用テキスト 未来を拓く探究シリーズ「探究ナビ」Benesse 参照
※1年学習シート①②
【2学年】***うごく・つながる【やまがたの未来をデザイン(よりよく)する】****
5月 地域創生講話を聴き、視野を広げるとともに「探究のタネ」を探す芽を育てる
広い視野で人々と力を合わせて共に生きる社会をつくるために、地域に深く根ざしてご活躍されておられる3名の方を講師にお招きし、地域創生講話を開催しました。
- 大山精機専務 大山 真吾 様
- 果樹園経営 結城こずえ 様
- 社会福祉士 柴田 邦昭 様



第1回は、大山精機の大山真吾様より「君たちが創る価値の羅針盤」と題してお話しいただきました。 「何のため(目的)を考えれば、本当のニーズを見つけられるということを知り、「イノベーション創出思考法」では、「新しい価値」のとらえ方や付加価値をつけることの大切さなどを学びました。
第2回は、山形まるつね果樹園の結城こずえ様より農業支援についてお話しいただきました。結城様は、ニューヨークの国連本部にて、国連女性の地位委員会でスピーチの経験をお持ちで、また、やまがた農業女子ネットワークの発起人でもあります。何事も前向きに行動してみることの大切さを学びました。
第3回は、社会福祉士の柴田邦昭様に、「私たちの生活と福祉」と題してお話しいただきました。講話の最後には、柴田様より「未来を担うキミたち一人一人が『誰かを思いやる気持ち』を持つことが地域の力になる」とのメッセージをいただきました。
6月 課題を見つけ、テーマを探る
新聞や市報、広報誌などから気になるワードを拾ったり、山形県の様々なデータを分析したりすることを通して、地域を知り、山形の良さや課題を見つけました。自分が興味を持ったキーワードから「自分がやりたいことは何か」「社会で求められていることは何か」「今の自分が技術的にできることか」を改めて自己に問いかけながら探りました。
7月 テーマを設定し、解決方法を探る 見通しを持つ
課題設定に向けたビジョンシート(本校作成)を用いて、探究の具体的なビジョンを明確に持ちました。ターゲットを明確にし、どんなことをねらいとして、誰とつながると上手くいくかを考え、具体的にどんな行動を起こしていくかを考えました。
※2年ワークシート①②③
【3学年】さぐる・たしかめる【社会に貢献で見る未来の自分をデザインする】
4~5月 課題研究テーマ決定に向けて
本校の高校の先生を講師に迎え、「課題研究」について講義をいただきました。3年では、個々の興味関心に基づき、社会の多岐にわたる分野から、テーマを見つけ研究していきます。リサーチクエスチョンとは何かということや、リサーチクエスチョンをより焦点化して検証を進めていくことについて、先輩方の実践例をもとに学びました。情報収集(先行事例・先行研究)⇒リサーチクエスチョン⇒仮説⇒検証方法の検討⇒検証(調査・実験)⇒結果の考察⇒新たな仮説 というプロセスで、実践を通して学びます。
6月 リサーチクエスチョンを導く
個々の興味・関心のあることをキーワード化し、そのキーワードについて定義を明らかにし、学術分野に分類します。それに関わる先行研究を調べ、具体的な「問い」を立てます。「問い」を立てるために、関連する知識を広げたり整理したりしながら、キーワードに刺さっていきます。生徒それぞれの興味・関心を掘り下げるということは、生徒自身の今後の進路選択や生き方にも関わるものであるととらえます。問いに対する答えを導く難しさと、その楽しさや喜びを味わうとともに、他者と協働して課題に向かい、飽くなき探究心を醸成しています。
※本校使用テキスト「課題探究メゾット 2nd Edition 」(啓林館)参照
※3年学習シート①②③④⑤
7月 リサーチクエスチョンの設定 検証方法を探る
「問い」から「リサーチクエスチョン」を導き、仮説を立てて(答えの予想)、研究の方向性を定めます。ゼミの先生にグループごとプチプレゼンテーションをし、助言をもとにRQ, 仮説、検証方法を検討しました。プレゼンテーションの視点として次の5つを挙げました。
■リサーチクエスチョン(RQ)
■問題の所在(研究の目的や意義、言葉の定義)
■先行研究・先行事例(この問題に関する現状・自分たちの研究との違い)
■研究の仮説(RQに対する「答え」の予想)
■研究の方法(RQの答えを導き出す手法)
ゼミ担当教員は、問い返し、リサーチクエスチョンの内容がより明確になるように指導しました。あやふやなリサーチクエスチョンは、これまでのワークシートを振り返らせ、クエスチョンマッピングを活用しながら導き、先行研究等の情報収集に努めるよう助言しました。
8月5日(火)に、SS総合探究Ⅱで「セイタカアワダチソウが持つ発芽・生長抑制物質の可能性」というリサーチクエスチョンを引き継いだ高校2年次3名が、日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 神戸医薬研究所へ見学に行き、ラボの見学や多くの研究者からアドバイスをいただきました。
最初、神戸医薬研究所 所長 和田耕一様から薬に関する講演をお聞きし、新薬開発についての概要を学びました。新薬ができるまでの道のりは長く、新薬誕生の成功率は3万分の1とのことで、大変な苦労を強いられる現状を知ることが出来ました。その後、ラボ見学を実施していただき、最先端機器類が整然と並んでいる様子も見ることができ、研究所の規模大きさに圧倒されました。次に、本校の生徒たちが、10数名の研究者を前にして「セイタカアワダチソウが持つ発芽・生長抑制物質の可能性」のテーマで研究発表も行いました。生徒たちは様々な角度からの質問に困りながらでも何とか答えていました。最後に、研究所の職員の皆様から今後の研究についてのアドバイスもいただきました。私たちが思いつかない観点での研究の方向性など大変勉強になりました。
実際の資料分析やこの訪問をご計画頂いただいた神戸医薬研究所の立石様をはじめ、多くのスタッフの皆様にお世話になりました。本当にありがとうございました。
8月6日(水)と7日(木)は、神戸国際展示場で行われた令和7年度SSH生徒研究発表会の見学を行いました。ここでもレベルの高い研究を聞いて、その質の高さに驚いた様子でした。今後の研究の継続に期待しています。
【生徒の感想】
・今回は大変貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。
・私は今回の見学で、様々な新しい発見をし、
・今回参加したSSH生徒研究発表会では様々な学校の研究を聞いた




令和7年7月22日(火)、23日(水)の2日間、また、高校2年次生がSS総合探究Ⅱの一環でフィールドワークを行い、各グループの探究テーマに沿って官公庁や企業などを訪問しました。
7月22日(火)には、山形大学STEAM教育センターの先生方とオンラインでつながり、生徒自身で各先生方に自分たちの研究のプレゼンを行いました。そして、各班の生徒たちが具体的な研究内容や研究方法などに関して、ご助言をいただきました。
また、同日、本校のOBである山形大学 大学院理工学研究科 2年 村田桃香様より、大学院での具体的な研究内容や研究生活等について講演をしていただきました。この講演の中で研究室に入って良かったことは、先行研究をベースにした研究デザイン力が育まれたという点を挙げていました。生徒の皆さんから多くの質問もあり、先輩から良い刺激を沢山いただいくことができました。
様々な機会を通じて、生徒たちは今後の探究活動の方向性がより具体的になったようです。10月8日(水)の中間発表会が楽しみです。
村田先輩の講演会と山大STEAM教育センターの先生方の指導の様子



6月3日(火)の6・7校時、高校2年次SS総合探究Ⅱにおける「研究計画書」発表会を実施しました。この会では、研究分野ごとに分かれた教室で、事前に作成した「研究計画書」に基づいて、班ごと発表・質疑応答を行いました。この会を経て、これから行う課題研究に具体性を持たせることが狙いの一つです。
本校で教育実習が行われている期間ということもあり、6名の実習生にも参加していただき、活発な意見交換ができました。生徒にとっては、今後の研究に向けた具体的な活動を考える上で、大きな収穫となったようでした。


12月5日(木)と6日(金)に東根市の天然記念物指定区域にて行われた、カクレトミヨ推定個体数調査に、本校2年生の課題研究でカクレトミヨの保全に取り組む4名が、東根市と清流の里おおとみ保全推進協議会、山形大学(半澤直人名誉教授)らと共に、トラップの設置からトラップの回収と捕まった個体数の確認までの調査に参加しました。初日は冷たい雨が降る中の作業でしたが、胴長を履いて川に入り、二日間頑張って調査を行いました。初日の様子はTUYのNスタ山形で放送され(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tuy/1599540?page=2)、二日目の様子は山形新聞でも紹介されました(下の写真)。
カクレトミヨは東根市が市の魚に指定している絶滅危惧IA類の生物ですが、高校生の認知度は残念ながらまだ低いと思われます。四人の研究が来年度は後輩に引き継がれ、カクレトミヨの保存に貢献していくことを期待しています。
令和5年7月21日(金)、24日(月)の2日間、また、それぞれ夏休みの時間を使って高校2年次生がSS総合探究Ⅱの一環でフィールドワークを行い、各グループの探究テーマに沿って企業や官公庁などを訪問しました。文系テーマの「東根市の小中学生に国際理解の新しい価値観をもたらすことはできるのか」について探究をしているチームは、仙台市のJICA東北を訪問し、彼らのメインの調査地域であるアフリカの基礎知識や現状、アフリカでのJICAの取り組みに加え、国際支援の仕組みやセオリーについても担当の職員の方から説明を受けました。生徒たちはそれぞれに疑問を持ち、講話を聞いた後は活発な質疑が行われました。今回JICA東北を訪問した3名のうち2名の生徒は文部科学省の留学支援プロジェクト「トビタテ留学JAPAN」から支援を受け、この訪問後ルワンダに渡航しました。日本、海外それぞれでのフィールドワークを経て、探究活動がさらに深まることが期待されます。
また、校内では理系の探究テーマに取り組んでいる複数のグループの生徒に向け、株式会社山形テレビが主催する「環境SDGsワークショップ」の一環で、山形大学理学部教授 栗山恭直先生に本校へお越しいただき、SDGsの視点で科学的な課題にアプローチする手法について講演いただきました。講演後は各グループの探究内容に関するご助言をいただき、参加生徒にとって有意義な時間になったようです。
夏休みが明けると2年次生は10月11日に行われる中間発表会に向けて、追実験・調査を行ったりポスター発表などの準備をすることになります。今後の2年次生の探究活動での活躍にもご期待ください。
中学校2年生の未来創造プロジェクトの取り組みが、7月24日の山形新聞に掲載されました。
中学2年のテーマは「やまがたの未来をデザイン(よりよく)する」です。キーワードは「うごく・つながる」で、社会とのつながりの大切さや山形への愛着心を育て、社会や地域のために自分たちが行動していくことをねらいとしています。























